アロマテラピーを始めたいけど、失敗しそうでなかなかできない!
という人に知ってほしい、失敗しない精油の選び方10の条件をご紹介します。
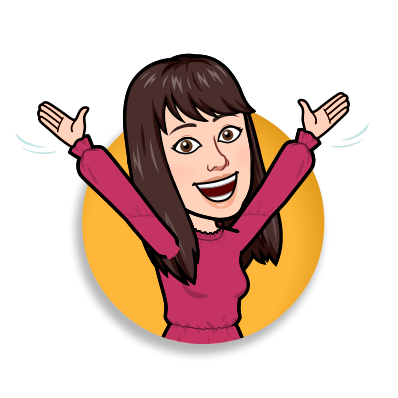
植物の芳香成分『精油』を使った療法なので、精油選びがめっちゃ大事!
失敗しない本格的な精油の選び方がわかるようになります!
はじめに
とりあえず、お店に並んでいるものは良い香りがしてリラックスできるのかな?
と買ってみたはいいけど、家に帰ってから効果がわからないよって人は多いと思います。
何が効果があるの?
気のせいかも?
みたいな話はよくあることです。
効果的な精油を使わなければアロマテラピー(芳香療法)にはならないんですね。
ですので、アロマテラピーを始めるには「選び方」が大事です。
この記事では、今までアロマテラピーをしたことがない初心者さん向けに、
読みやすいアロマで使用できる精油の選び方を分かりやすくお伝えします。
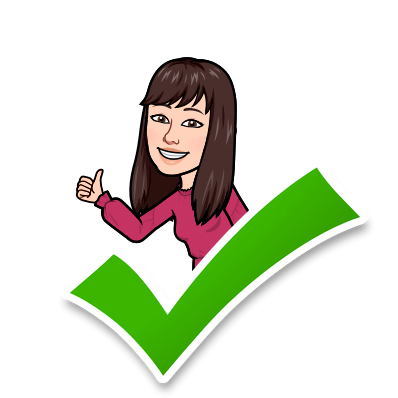
この記事を読み終えると、アロマテラピーの初歩が分かるので、習いにいかなくても簡単にアロマライフが過ごせるようになりますよ♪
精油の選びかた
香料用とアロマテラピー用があるって、ほんと?
はい。
ほんとうです。
香料用に抽出されてる精油とアロマテラピーで使う精油は品物が違います。
さて、何が違うかとゆうと、香料は食品や日用品、香水などの香りを付ける原料として、
世界中で広く使われています。
もしかしたら、現在流通されている精油のほとんどは香料用の精油かも?
って話があるくらい、
アロマテラピーで使用できる精油は、ごくわずかな量しか流通してないのが現状です。

その違いをご紹介したいと思います。
精油は何からできているのか
植物は生き物ですから、天候や土壌の自然の条件によって変化するものです。
わたしがよく使う例え話は、スイカ(笑)去年のスカイと今年のスイカの味。
まったく同じかって?年度のよって微妙にちゃうやろう~~~。
それが自然とゆうもんですね。
でも、商品としての香料精油としたら、いつも同じではないと
”商品”にはならないので、常にメーカーが決めたものを一定の香りに調整しています。
これだけでも、ビックリするんですが、コスト削減のために合成香料を混ぜたり、
前年の残りをまぜたりすることもあるようです。
(ひぇ~~~~~)
前年の残りを混ぜたりするとは。。。
そこで。
市販されてる数々の精油の中から、アロマテラピーに使える精油を見分ける
10の条件を参考に購入してくださいね。
アロマテラピーで使用できる10の条件
ちなみに成分分析といわれても素人じゃサッパリわかりませんよね。
わたしも成分分析は苦手分野でした。
以前に京都大学大学院のT先生(分析専門)の講座を受講した際に、
実際の精油の成分分析の詳細を教えていただきました。
一般的には、ガスクロマトグラフィーという精密機械で分析するんですが、
それに質量計を付けて初めてきちんとした分析ができるとのことでした。
また、分析した結果を公表していないと、ケモタイプ精油とは認められません。
公表しているものでも専門家以外のわたしが見ても?な分析表もあります。
また、蒸留はその植物にとって旬なとき、旬の手前に蒸留されます。
いつ蒸留されたのか表示のない精油は、売れ残った精油の寄せあつめかもしれません。。。
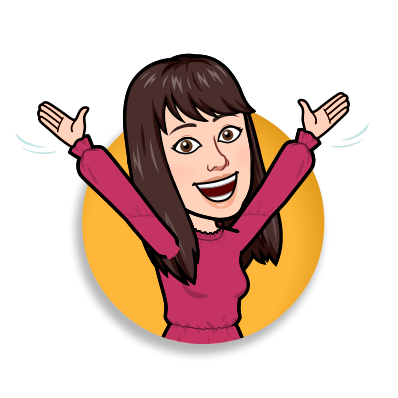
アロマテラピー(芳香療法)として使うのなら、効果が期待できるもの。
きちんとした精油を使いたいですね。
アロマテラピーとして使うのなら、新鮮なものを新鮮なうちに使いたいものですね。
成分分析とか聞いたら、なにやら難しそうで、できるだけ避けたいような気がします。
実はわたしも初めはそんな感じでしたけど、わかると面白くなってきました。
精油成分のひみつ
なぜ、心や体に良い効果が期待できるのか?
精油の分析表は主にガスクロマトグラフィー(ガスクロ)と、質量計で分析した、
植物の有用成分の含有量を数値で表わしたもの、のことです。
一つの植物に数種類の成分が入っています。
人間が調整できない絶妙なバランスで。
まだまだ計り知れない成分もあるようです。
100%純粋とか、天然とか、無農薬とか、有機栽培とか。
各メーカーがネーミングをそれぞれ工夫してますが、
一般的に見ると、よくわからない、ことがほとんどです。
なるべく多くの情報を公開してるメーカーの精油が、
消費者にとっては安心して使用できるのではないでしょうか。
あと、輸入の際の製造者責任は輸入元にあるので、
輸入後の成分分析を国内でチェックできてるか?とか。
空輸なのか、船便なのか。
いわば、生き物の精油は現地での分析とは異なってきます。
(どのように輸入しているのか?メーカーに直接聞いてみたらいいかもしれませんね。
教えてくれるかわかりませんけど)
アロマテラピーでは、有用成分が含まれていてこそ、確実な効果を期待することができます。
よく、雑貨店にある精油のようなものは、良い香りがするものがあるかもしれません。
とはいえ、雑貨品は雑貨なので、療法として使用するには相応しくありません。
使用方法を間違えると不要なトラブルを起こす可能性があります。
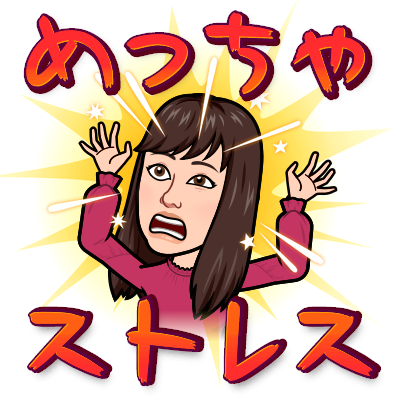
わたしなんか、かつては生理前のイライラなんかで、精油が大活躍しました。
どうにかこうにか、生理期間を過ごしたいものですよ。
まとめ
今回は、アロマテラピー初心者さん向けに、
アロマテラピーで使用できる精油の選び方を10の条件としてお伝えしました。
最後におさらいをします。
●アロマテラピーは条件がわかる「精油」を使う
●雑貨品は使用しない
●精油の成分分析結果がわかるも品物が安心
初心者では、わかりにくいと悩んでいたアロマ初心者さんでも、
精油選びができるようになれば、簡単に自分でアロマライフが送れるようになりますよ。
しっかり実践して身につけていきましょうね!

以上、参考になれば嬉しいです。
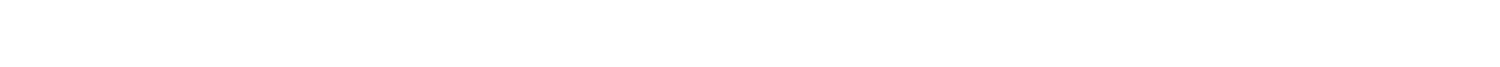








結構有名な先生が約1000人以上おられるであろう会場でおっしゃっていました。
『だいたいのメーカーは香りが一定になるように混ぜてますね~』って。
こんなとこで、そんなんゆうていいんかいな?と思いましたけど。
混ぜてる時点で天然ではない、とわたしは思うんですけど。
天然は天然でも、そこには混ぜているという人為的な作業があるわけでしょ。
(人工的な匂いのする液体よりはマシかもしれへんけど)